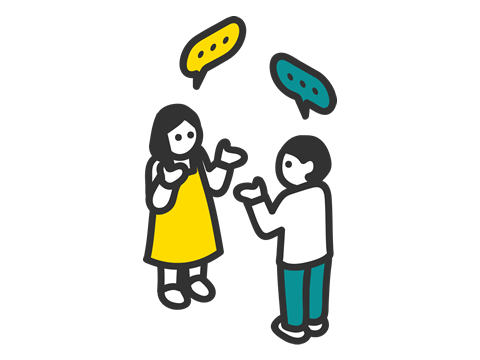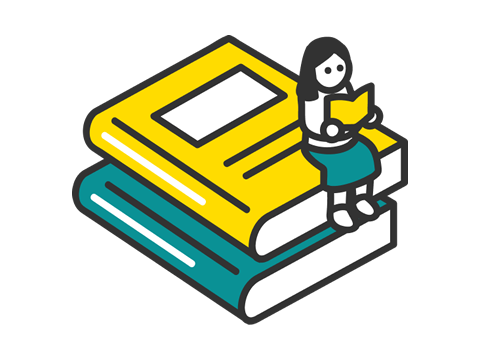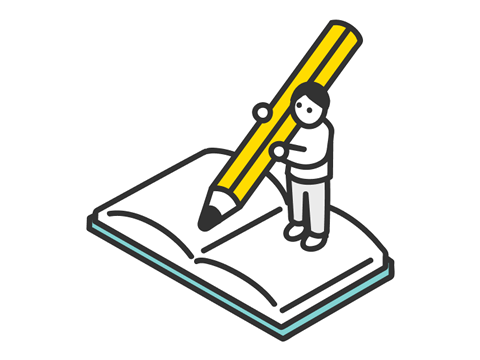コラム
2025.10.20
子供の「つらさ」に目を向けてみませんか
不登校の背後にある子供の傷つき体験

目次
不登校は子供のSOS
「どうして学校に行けないの!」「怠けていないで、学校に行きなさい!」
不登校になったお子さんに、そう声を掛けたくなるお気持ち、よくわかります。
でも、まずはこう考えてみてください。
お子さんは学校へ「行きたくても行けない」ほど、つらいのかもしれない。そう考えてみてほしいのです。
実際、不登校の子供たちの多くは、心や身体に不調を抱えていることが、既に多くの研究からも分かっています。
例えば、とある調査では、不登校の児童生徒の多くが「不安」「抑うつ」などの心の不調や、「頭痛」「腹痛」などの体調不良を訴えていることが明らかになりました。
つまり不登校は、子供の「怠け」や「気分」の問題ではなく、心身のSOSである可能性が高いのです。
背後にある「傷つき体験」
では、そうした「心身のSOS」は、なぜ生じているのでしょう?
不登校の子供の多くは、いじめ被害や「先生と合わない」などの人間関係でのトラブルや、学校の勉強についていけないなどの学習に関する困難などを訴えています。
こうした心理的に負荷がかかる体験、「傷つき体験」が、心身の不調を引き起こし、結果として学校に「行きたくても行けない」状況をつくっている可能性があるのです。大人にとっては、大したことではない、と思うようなことでも、子供にとっては、人生最大につらい「トラウマ」になることがあります。
傷つきやトラウマは、外から確認することができません。また、子供本人すら自分自身の傷つきやトラウマに気づいていないことも珍しくありません。
問題行動ではなく、「傷つきのサイン」
傷ついた子供は、不登校に限らず、以下のような様子を見せることがあります。
- キレる、パニックになる
- 不信感が強く、人を試すような態度
- 避ける、話をはぐらかす、考えられない
- 平然としていたり、やたら明るくふるまう
- ぼんやりしていて記憶があいまい
わが子がこうした様子や行動を見せていたら、つい、その「行動」に目が行ってしまいますが、少し見方を変えて、「この行動の背景に、何か傷ついた体験をしたのではないか?」と考えてみてはいかがでしょうか。
これらは「問題行動」ではなく、「傷つきのサイン」かもしれません。傷ついた子供にとって大切なのは、「傷を癒す」ことです。
「ポジティブな体験」が癒しを助ける
では、どうすれば傷は癒されるのでしょう?
それはずばり、「ポジティブな体験」です。特別なことではなく、家庭の中でできることもあります。例えば、親子でお互いに今日の気持ちを話す時間を、1日5分だけでも持つのはどうでしょうか。
その際、次のことを意識してみてください。
- 子供の言葉を否定せずに聞く(評価せず受け止める)
- 「ありがとう」「うれしかったよ」など、感情を伝える
- 安心して過ごせる空間(叱責・比較がされない場)を作る
こうした「ポジティブな体験」を積み重ね、「この家は、安心できる」「親に大事にされている」と感じられると、子供の回復力はぐっと高まります。
自分だけで上手くできるか心配、という方は、家庭の外に頼るのも大切です。
- 家族以外にも頼れる大人(祖父母・近所の信頼できる大人・学校の先生・塾や習い事の指導者など)を意識する
- 地域の活動(お祭り、ボランティア、子供会など)へ積極的に参加する
このサイトでは、官民の様々な支援情報を見つけることができるので、ご自身やお子さんに合いそうなサービスを一緒に探してみると良いでしょう。
不登校は「終わり」ではない
「いつになったら学校に戻れるのか?」
「勉強はどうするのか?」
そう考えてしまうお気持ちも無理はありません。けれど、不登校も、傷つきも、「終わり」ではありません。大切なのは、子供の力を信じ、急がず、ゆっくりと寄り添っていくことです。
あなたやお子さんを支えてくれる人はたくさんいます。一緒に一歩ずつ進んで行きましょう。
NOTE
トラウマ
トラウマとは、強い恐怖やショック、不安などを感じる出来事によって、心に深く残る傷のことを指します。
トラウマを生むのは「死ぬような体験」だけではありません。例えば、何度も繰り返された叱責や無視や理不尽な扱い、逃げ場のない孤立感なども、子供の心には大きな負荷となり、トラウマとなることがあります。
記事を監修した人

所長・主席研究員
特別支援学校の教師として20年以上勤務した後、小児発達学の博士号を取得。専門は子供のいじめや不登校など。
【参考文献】
■子どもの発達科学研究所(2024)、文部科学省委託事業 不登校の要因分析に関する調査報告
https://kohatsu.org/20240325research-report/
■学校ACE研究(2023)
https://kohatsu.org/school_ace/
■PCE研究:Positive Childhood Experiences and Adult Mental and Relational Health in a Statewide Sample, Associations Across Adverse Childhood Experiences Levels
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2749336