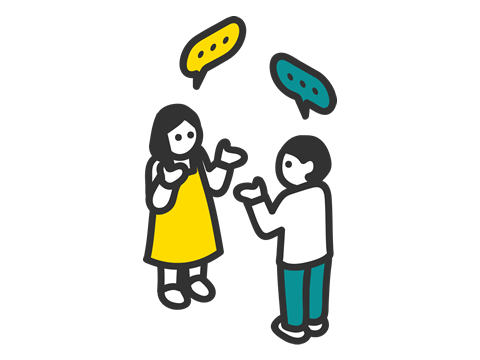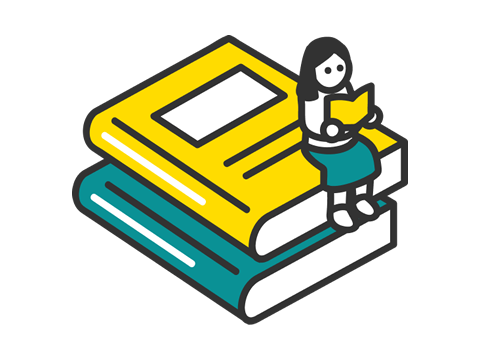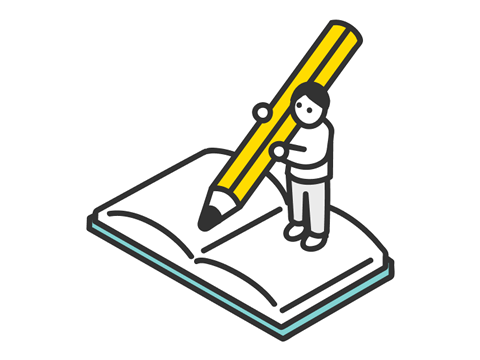コラム
2025.10.20
発達特性や感覚過敏がある子供への支援
「行けない理由」を子供自身が話せるとは限らない
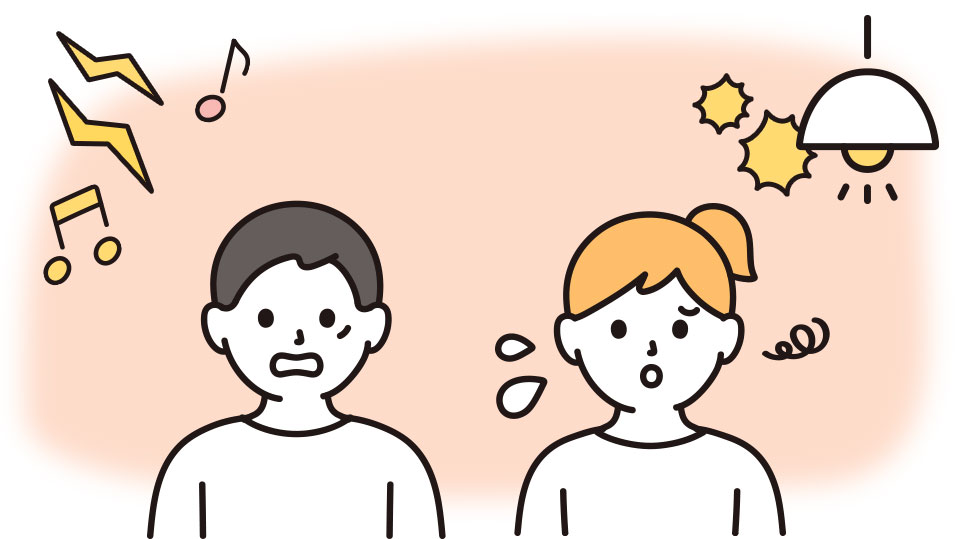
目次
朝になると、なんだかうまくいかない
学校に行こうと思っているのに、身体がついてこない……。
子供は「行けない」と感じても、その理由をうまく説明できないことがあります。
学校は、すべての子供にとって「安心できる場所」とは限りません。
音の響き方や蛍光灯の光、教室特有のにおい──。
感覚が敏感な子供の場合、そうした刺激が重なると、集中が難しくなったり、強い疲れを感じたりすることがあります。
そこに突然の時間割変更や席替え、大きな声での指導などが加わり、「学校=安心できない場所」だと感じてしまうことがあるのです。
そのような環境が続くと、ある朝から、子供はこう感じるようになるかもしれません。
「学校へ行ったら、今日もまた、つらいことが起きるかもしれない」
これは、怠けやわがままではありません。「その場所から離れることで自分を守ろうとする、こころと身体の反応」です。
ここで大切なのは、こうした“感じやすさ”は、生まれつき人によって異なるということ。
そのため、子供自身は、「自分だけがそうなのか」「みんなも同じだけど、自分だけがうまくできないのか」が分からず、ひとりで苦しんでしまうことがあるのです。
「発達特性がある=不登校」とは限らない
特に、自閉スペクトラム症や注意欠如・多動症などの発達特性がある子供たちの中には、音や光、人との距離感などに対して、独特な感覚の捉え方や反応の強さを示す子供が少なくありません。
そのため、こうした発達特性のある子供たちは不登校になる傾向が大きいことが、これまで多くの研究で報告されています。
けれど、傾向が大きいからといって、発達特性のあるすべての子供が不登校になるわけではありません。
実際に、文部科学省の調査では、発達障害やその疑いのある子供たちのうち、約8割は不登校ではないことが明らかになりました。
もちろん、地域や調査によって数値は異なりますが、「発達特性があるからといって、必ずしも学校に通えなくなるわけではない」という事実は、大切にしたい視点です。
登校を続けている子供の共通点
では、発達特性がありながらも学校に通い続けられている子供たちには、どのような共通点があるのでしょうか。
文部科学省の調査では、次のような要素が、発達特性がありながらも登校を続けている子供たちに共通してみられる項目として確認されました。
- 家庭や学校に「安心できる人」がいる
- 部活動や学校外の地域活動などに参加している
- 自分なりの「将来の夢」や「やってみたいこと」を持っている
つまり、子供自身が学校や家庭、地域などに「ここには自分の居場所がある」と感じられることが、子供が学校や社会とつながるためのポイントです。
子供が社会とつながるためのヒントは、“理解される体験”
子供が学校や社会とつながっていくためには、そうした安心できる環境や居場所の整備が必要です。
そして「安心できる環境」だと感じられるためには、「自分の感じ方や困りごとを、ちゃんと分かってもらえた」という体験が必要です。
例えば、
- 音やにおい、予定変更など、苦手な刺激への配慮がされている
- 「叱る」のではなく、一緒にやり方を考えてくれている
- 苦手なことだけでなく、得意なことにも気を配ってもらえる
- 「あなたはダメ」ではなく、「あなたにはこうすればできる」と前向きな言葉を掛けてもらえる
こうした経験の積み重ねが、「ここならやっていけるかもしれない」という気持ちを育てます。
まずは家庭から。そして学校などにも相談しながら、少しずつ子供たちをとりまく環境を「安心できる」ものへと整えていけるとよいのではないでしょうか。
「どうして行けないの?」ではなく「何があったの?」
子供が学校に行けなくなったとき、私たちはつい「どうして?」と、子供自身に原因を求めがちです。
しかし冒頭でも述べたとおり、子供は自分の感覚や「行けない理由」を、うまく言葉にできないことが少なくありません。
そこで、問いを少し言い換えてみてください。
「何があったの?」
そう問うことで、子供の抱えるつらさや困難を生み出している環境の存在に気づけることがあります。
その気づきが、発達特性や感覚過敏がある子供の支援の出発点です。
記事を監修した人

准教授
大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程修了。 東海学院大学、弘前大学大学院医学研究科附属子どものこころの発達研究センター、弘前大学医学部心理支援科学科を経て、現職。
【参考文献】
■子どもの発達科学研究所(2024)、文部科学省委託事業不登校の要因分析に関する調査報告
https://kohatsu.org/20240325research-report/