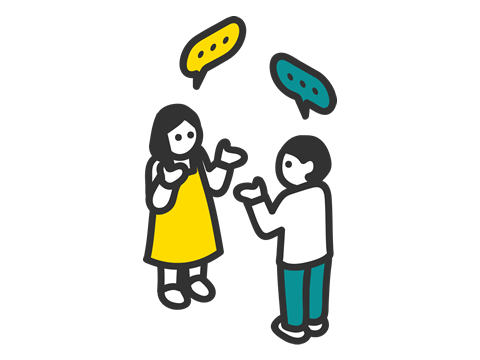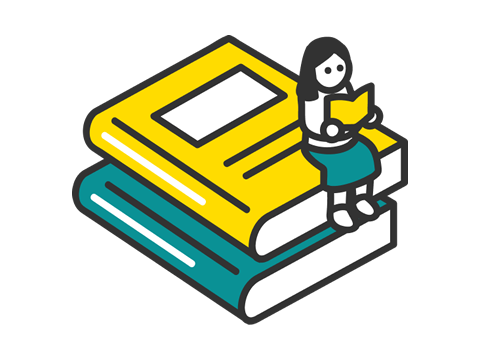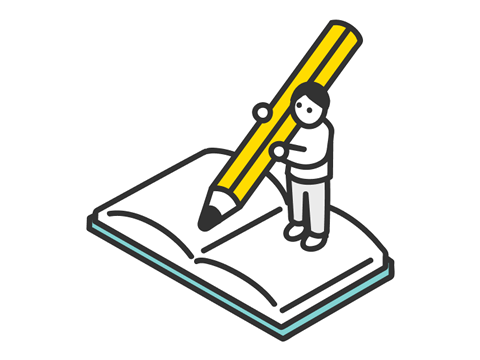コラム
2025.10.20
親子で使える福祉サービス
大人の幸せは子供の幸せにつながる

目次
不登校は親のせい?
このコラムの監修者・黒光さおりさんに、お話を伺いました。
スクールソーシャルワーカー(SSW)をしている私のところに、ある親御さんが子供の不登校について相談に来て、次のような質問をされました。
「不登校の子供をもつ親には共通点がありますか?うちは子供2人とも不登校で……私のせいではないかと」
私は答えました。
「共通点はあります。“親のせいではないか”と自分を責めることです。不登校は育て方が原因ではありません。」
自分を責めてしまう方は本当に多いです。けれど、子育ては保護者や家族だけではなく、みんなで支え合い、助け合うものです。
大人にも味方が必要です。不登校やひきこもり、メンタルヘルスなど、子供を取り巻く課題が注目されていますが、子供だけが困っているのではありません。
「大人の孤独」や「育児の孤立」が先にあり、サポートが得られないと子供にも影響します。
大人が安心して生きられることが、子供の安心にもつながります。
「頼る」ことをためらわないでください。そうすることで、子供が将来困った時の手本にもなります。
相談に来られたご家庭のエピソードをいくつかご紹介します。
学校以外にも専門職の味方をつくる
相談に来られた親御さんの子供Aさんには、コミュニケーションの苦手さと読み書きの難しさがありました。そこで障害児相談支援事業所を紹介。発達検査を受けた結果、学習障害(LD)があり、発達支援の必要性があることが分かりました。
放課後等デイサービスに通い、Aさんに合った方法で発達支援を受けることでできることが増え、友達もできました。学校ではタブレットで板書をとれるようになり、授業についていけるようになりました。
【関連のある制度】
- 東京都発達障害者支援センター…発達に心配がある方の相談・支援窓口
- 児童発達支援センター…地域の障害児支援の中核的役割を担う機関として、主に就学前の障害のある子供又はその可能性のある子供に対し、障害の状態や発達の状況、障害の特性等に応じた発達上のニーズに合わせた発達支援や家族への支援を行う。
- ペアレントメンター…発達障害のある子供の養育経験がある相談員
- 放課後等デイサービス…学齢期の障害のある子供に対し、障害の状態や発達の状況、障害の特性等に応じた発達上のニーズに合わせた発達支援や家族への支援を行う。
不登校により家族のバランスが崩れたら……
不登校の子供がいると、きょうだいも親の関心を引こうとして手がかかるようになることがあります。
不登校のBさんのお母さんがBさんの支援に奔走する中、3歳の妹が駄々をこね暴れることが増えました。でも、お母さんの体は1つだけ。家事だってたくさんあります。お母さんはとても頑張り屋ですが、1人で2人の難しい状態の子供に対応するのは限界があります。
そこで、Bさんが日中を過ごせる児童館を紹介し、その間にお母さんが妹とゆっくり過ごす時間を作りました。
また、妹は自治体の一時預かりを利用し、お母さんがBさんの支援に専念できる時間や、お母さん自身のリフレッシュの時間を作りました。妹は、のびのびと遊べる時間や、家族以外の大人と関われる時間が増えました。
Bさんは居場所や友達とつながることができ、妹は駄々をこねることが減り、お母さんも気持ちに余裕ができました。
【関連のある制度】
- スクールカウンセラー…学校で子供や保護者の相談に乗る心理の専門家
- 教育委員会の相談室…学校生活や家族関係などの相談窓口
- 児童館、子供食堂など…地域で安心して過ごせる居場所
- 一時預かり事業…出産・病気・冠婚葬祭などのほか、子供からちょっと離れたいときなどに子供を預けられる制度
- 幼稚園の預かり保育…幼稚園の教育時間の終了後に子供を預かる制度
介護との両立のサポート
子供の不登校と祖父母の介護が重なる家庭もあります。
不登校のCさんは、両親と、要介護認定を受けた祖母と暮らしています。祖母は、ホームヘルパーに来てもらって、日中のケアを受けていました。ただ、学校に行けないCさんと外出できない祖母はいつも2人きりでした。祖母はいつもCさんを心配していてふさぎ込みがちになりました。そんな祖母を見て、Cさんも、つらい気持ちを覚えるようになりました。
そこで、Cさんの親御さんがケアマネージャーに相談したところ、デイサービスの利用を提案してくれました。祖母や家庭の状況を踏まえてケアプランを見直してくれて、週3回デイサービスを利用できるようになりました。外での交流で祖母の笑顔が増えました。
Cさんが祖母を迎えに行く時には、他の高齢者と挨拶すると喜ばれるようになり、人との関わりに慣れ、外出する意欲がでてきました。現在は高校進学を目指して別室登校をしています。
【関連のある制度】
- 介護支援専門員(ケアマネージャー)…要介護者や家族の状況等に応じた適切な介護保険サービスが利用できるよう、介護保険施設等との連絡調整等を行う。
- 訪問介護…ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事や排泄など日常生活上の介護や、調理や洗濯などの生活援助を行う。
- 通所介護(デイサービス)…施設に通い、食事、入浴などの日常生活上の支援や、機能回復のための訓練・レクリエーションなどを行う。
それぞれの制度には利用条件があります。利用のための手続きについては、スクールソーシャルワーカー(SSW)や、区市町村の子育て相談窓口などに相談してみましょう。子育て相談窓口は、このポータルサイトで探すことができます。
公的支援に加え、民間団体による地域の居場所も増えています。社会福祉協議会や公共施設の情報コーナーなどで情報を集めるのもおすすめです。
家族だけで頑張り過ぎない
子育てをしている保護者の方は、頑張り屋さんが多いです。でも、頑張り過ぎないでほしいです。制度や人、場所を活用し、支え合って子育てをしましょう。
保護者や家族が少し楽になることで、不思議と子供の状態が良くなることもある、ということを、ぜひ心に留めておいてくださいね。
NOTE
スクールソーシャルワーカー(SSW)
関係機関とのつながりを活用し、子供のおかれた状況をよりよくするための支援をする福祉の専門家です。
記事を監修した人

社会福祉士 公認心理師 特別支援教育士
14年間の生活保護ケースワーカーを経て、尼崎市の小中学校および兵庫県長田商業高等学校でスクールソーシャルワーカーとして勤務。