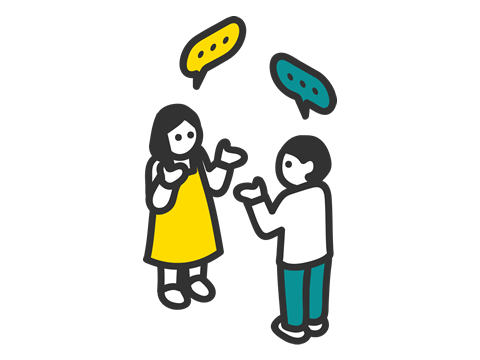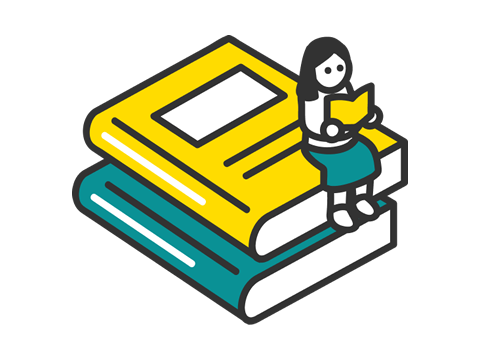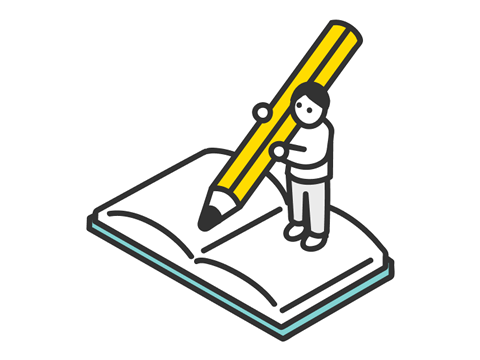コラム
2025.10.20
わが子の不登校に戸惑うあなたに
保護者自身の気持ちの整理と家庭内のズレや葛藤を乗り越えるために

目次
不安になるのは当たり前
「不登校」という言葉は、誰しもが知っている言葉になりつつあります。
しかし、いざ自分の子供が学校に行けなくなると、「まさかうちの子が……」「どうしたらいいかわからない」といったショックや戸惑いを覚えるのではないでしょうか。
不安に襲われ、「育て方が悪かったのではないか」「しつけが甘かったのでは」といった罪悪感を抱いてしまう方もいるでしょう。
とはいえ、これは当たり前の自然な反応です。最初から冷静に状況を受け止めたり、支援先を頼ったりできる人は、ほとんどいません。
心の変化のプロセス
不登校を受け入れるまでには時間がかかります。そのことを知っているだけで、少しだけ心がラクになるかもしれません。
最初は「きっと一時的なものだろう」と受け入れられず、周りを頼ったり、アドバイスをもらったりすることは難しいのではないでしょうか。
また、登校を促しても、無理に連れて行っても改善しないといった試行錯誤をして行く中で、疲れを感じることもあるでしょう。
そうした時期を経て、徐々に子供の不登校と向き合えるようになると、周囲を参考にしたり、学校以外の選択肢を探したりする気持ちが芽生えてくることもあるかもしれません。
そして、相談先や支援機関などで同じような経験をしている保護者や子供と出会う中で、「うちの子が特別なわけではない」と気づき、少しずつ子供のありのままを受け入れられるようになっていくのです。
家庭内に起こるズレと葛藤
しかし、家族全員が同時に、そうした変化をたどるわけではありません。
不登校は「子供の問題」と捉えられがちですが、実際には家族全体に大きな影響を及ぼす出来事です。
登校しない日が多くなるにつれ、家庭内の葛藤も目立ってきます。特に、子供と接する時間の長さによって、子供への対応や考え方に違いが生じることもあります。
家庭内で子供と接する時間が長く、日常的に登校を促す役割を担っていると、他の人より一歩早く「まずは休ませて様子を見たい」と思うようになります。
一方で、子供の様子を直接見る機会が少ないと、「甘やかしてはダメだ」「無理にでも学校に行かせるべきだ」と考え、家庭内で意見が対立してしまうことがあるのです。
また、子育ての考え方や価値観は世代によっても異なる場合もあり、祖父母世代などに相談したくてもなかなかしづらく、孤立感にさいなまれることがあります。
まずは心を落ち着けて
家族の葛藤を解決するために大切なのは、まずはあなた自身の心の安定です。
子供が不登校になることで、保護者が動揺するのはごく自然なことです。まずは、今感じている気持ちを否定せず、自分自身を大切にしてください。
「どうしたらいいのか分からない」「このままでいいのだろうか」。そのつらい気持ちを誰かに話すだけでも、心が軽くなることがあるはずです。学校の先生やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーのほか、教育支援センターや子供家庭支援センターなど、相談先はたくさんあります。
保護者が穏やかに安心してそばにいてくれることで、子供は「大丈夫なんだ」と感じることができるようになるのです。
とはいえ、登校できない子供と一緒に過ごす時間が、つらく感じられることもあるかもしれません。
そんなときは、周囲の人の助けを借りながらでいいので、リフレッシュする時間をつくるのもよいでしょう。
(参考)親子で使える福祉サービス
わずかな時間でも良いので、公園で散歩する、カフェでゆっくりする。そうした時間は、心をほぐすきっかけになります。
あなた自身の心に余裕ができてきたら、子供と一緒に好きなことをするのもよいかもしれません。
家族として乗り越えていくためには
気持ちが穏やかになったら、今度は、他の家族に気持ちを伝えてみるのはどうでしょうか。
家族のズレや葛藤を解消していくには、家族全体で気持ちを共有することが、とても大切です。
「子供の将来が心配だけど、無理に学校に行かせたいわけではない」「子供には元気でいてほしい」といった素直な気持ちを伝え合うことで、互いの立場や思いを理解し合えるようにしていくのです。
対話を重ねる中で、家庭内のズレや葛藤が少しずつほぐれていき、家族が一つの方向を向いて子供を受け入れていく土壌が育まれていきます。
あなたの心のサポートをしてくれる人はたくさんいます。
このポータルサイトでは、そうした支援を探すことができますので、ちょっとしたことでも、利用してみてくださいね。
記事を監修した人

博士(医学)/公認心理師/臨床心理士/公益社団法人子どもの発達科学研究所 客員研究員/東京都北区特別支援委員会委員